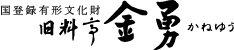旧料亭金勇の歴史について
| 料亭金勇は、初代金谷勇助(かねや ゆうすけ)氏が明治23(1890)年に創業し、木都能代を象徴する建物で、県内屈指の料亭として各種宴会や接待、婚礼などに広く使われました。
現在の建物は、昭和12(1937)年、2代目金谷勇助氏によって建てられたもので平成10(1998)年10月26日に国登録有形文化財に登録されました。 その後、平成20(2008)年8月末に閉店。翌21年に能代市に寄贈されました。能代市が寄付を受けた理由としては、天然秋田杉の良さを十分に活かし、重要文化財に登録されたもので、同様の再建築は不可能な貴重な建物であること、木都能代の発信基地として担える建物であること、以上の点が評価されました。 |
木都能代
| 能代は米代川の河口に発達した街です。米代川が交通の役目を果たし、上流の北鹿地域の金銀銅、木材などの資源や米を中心とした農作物などが集まり、南下して交易の場として栄えました。
中でも注目されたのが「秋田杉」で秀吉の求めで桧山城主安東実季(さねすえ)が大安宅船(だいあたけぶね)用材を送ったのが文禄2年(1593)。伏見城にも使われ「秋田杉」の名声は京都・大阪方面から広まったようです。 明治中期には、井坂直幹(なおもと)が機械製材を導入し、それまでの手加工に比べ生産量は飛躍的に伸びました。これが秋田木材(株)へ発展し、以来能代は東洋一の「木都」と呼ばれるようになりました。 |
金勇で使われている材料について
| 天然秋田杉は濁川国有林(金山)から切り出され、人力、森林軌道、筏を使って能代まで運ばれました。
能代市内は道が狭く、家を傷つけたり場所によっては家の一部を取り壊して運ばれました。持ってきた天然秋田杉はいい物を使い、残ったものは秋木が買い取りました。 天然秋田杉以外では、杉・松・エゾマツ・アカマツ・ベイマツ・ヒバ・ケヤキ・カエデ・サクラ・キハダなどが使用されています。その他の足りない材料は秋木や昭和木材にあったものを使用し、東京の篠田銘木店からも買い付けていました。 贅を尽くした使い方ではなく、選木した良材を有効的に使用していること、建物内に四方柾の柱が1本のみしかないことから、与えられた素材を無駄なく製材したことが窺えます。 |
旧料亭金勇の歩み
| 明治23年
(1890年) |
初代金谷勇助 現在地に貸席として山本倶楽部を創業 |
| 明治38年
(1905年) |
12月9日 彦兵衛からの火事により建物消失
同年再建 金勇倶楽部へ名称を変更 料亭として営業再開 |
| 昭和12年
(1937年) |
2代目金谷勇助 新館として現在の建物を建築
8月着工 9月上棟式 11月10日竣工 大工45人、人夫20人を常用 棟梁:梅田鉄三 副棟梁:荒木菊太郎(東京の宮大工) 建築後援会:昭和木材(株) 舘岡篤社長、秋田木材(株) 小沢秀治所長 等が資金や建築木材の調達に奔走 協力者:能代営林署 横川信夫所長、西田木材 西田正二社長、牛丸兵衛、竹内平蔵 等 |
| 昭和19年
(1944年) |
陸軍の徴用により、営業停止 三代目は軍属となる
陸軍所沢飛行場東雲分場が宿舎として使用 将校は小部屋、下士官は中広間、兵士は大広間を使用 |
| 昭和21年
(1946年) |
営業再開
昭和14年からの戦争で営業が振るわず、建築の借金が残っていた |
| 昭和26年
(1951年) |
料亭金勇へ名称を変更 |
| 昭和32年
(1957年) |
10月 旧館解体に伴い玄関を改築し、厨房を増築
舞台を改修し、空調を取付 |
| 昭和45年
(1970年) |
6月 大広間舞台に緞帳を取付 |
| 昭和54年
(1979年) |
上げ汐の間、曙の間、結婚式場などを増築 |
| 昭和58年
(1983年) |
日本海中部地震により一部損壊。照明などを改修 |
| 平成10年
(1998年) |
10月 国登録有形文化財に登録 |
| 平成20年
(2008年) |
8月 料亭金勇閉店 |
| 平成21年
(2009年) |
3月 4代目当主能代市へ寄贈 |
| 平成25年
(2013年) |
増築部分解体、耐震補強工事
12月 観光交流施設「能代市旧料亭金勇」として開館 |