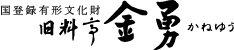能代の木材産業の発展に大きな役割を果たし、東洋一の木都と呼ばれるまでにした、木都の父。
以下、『郷土の先人たち』より引用
9-1 東洋一の「秋木」を築いた 井坂直幹(いさかなおもと)
井坂直幹は明治22(1889)年、東京の林産商会の支店長として能代にやってきました。水戸の生まれですがその半生を能代の発展に尽くした人です。
28歳で能代の土を踏み、長年の願いであった機械製材を実現させ、明治40(1907)年には東洋一の「秋田木材株式会社」を創設しました。
その他にも、植林事業をはじめ電気や鉄工業等にも着手し、能代の産業の発展に尽くした他、労働者の労働条件の改善や、生活に困っている人々を救うための社会事業などに功績を残しました。
更には、有能な青少年を進学させるための奨学資金を出したりしました。この奨学資金は戦後も続いていましたが、今は一時休止の状態になっています。
このように、井坂直幹は能代の産業だけでなく、人々の生活を豊かにするためにも、惜しみなく力を注いでくれた能代の恩人です。
9-2 直幹の生いたち
井坂直幹は、万延(まんえん)元(1860)年茨城県水戸市に生まれ幼名を亮太郎と言いました。
父は幹(もとい)といい、元水戸藩士で廃藩置県後は、茨城県や熊本県で役人をしたり、水戸で銀行に勤めたりした人です。母は美与といい留守がちな夫を助けて、田畑を耕やして家計を補い、子ども達の教育にも熱心な人でした。
亮太郎が15、6歳の頃、母と一緒に水戸の城下近くの寂しい野原を通った時、急にまわりの萱やすすきが、ざわざわと波打ったので亮太郎は思わず腰の刀に手をかけました。
それを見た母は、「武士の子が風の音にびくびくして、みだりに腰の物に手をかけるのは見苦しい。」と叱りました。このような母の影響を受けて直幹は、かなり気性の激しい子どもに育っていったようです。
直幹は13歳の頃から水戸学(江戸時代に水戸藩でおこった学問)を学び、15歳で当時水戸の秀才達が学んだ「自彊舎(じきょうしゃ)」という塾に入リました。
この頃武士の俸禄制度が廃止されたため、井坂家の家計はかなり苦しく、直幹は母と一緒に田畑で働き、夜は自宅から4キロメートルも離れた塾へ通って、熱心に勉強しました。
その後、水戸の「彰考館(しょうこうかん)」で大日本史の編さんに特に許されて従事することになった直幹は、昼は彰考館で編さんの仕事、夜は自彊舎に通う毎日でした。
その間また師を求めて英学を勉強し、新しい時代への準備を怠りませんでした。
当時、水戸には薩摩字引(さつまじびき)と言われた英語の辞書は1冊しかありませんでした。
直幹はその1冊の辞書を夜だけ借りて、自彊舎での勉強が終った後、夜中の12時頃から夜明けまで、毎日のようにそれを写しとったと言われています。
このようにして翻訳書(ほんやくしょ)を読み、英学の勉強をすすめていくうちに、欧化主義に賛成するようになりました。
そのため、自彊舎の人達との交わりも絶つことになり、彰考館も辞職するという苦しい立場に立ってしまいました。直幹は悩みの末、東京への遊学を決心しました。
しかし、家は学資を出せる程家計にゆとりが無かったので、直幹は親友を通して、英学の師であった水戸師範学校の校長松木直己に相談しました。
その頃松木は、自分の師である福沢諭吉から時事新報発刊について、将来記者にむく文才のある青年を頼まれていたので、直幹ら4人を福沢諭吉のところに送リました。こうして直幹は慶応義塾で学ぶことになったのです。
2年半にわたる慶応義塾を優秀な成績で卒業した直幹は、明治17(1884)年 福沢諭吉が発行していた時事新報社に入りました。
ここでは前後4年間編さん局翻訳係等を担当しましたが、特に土木・経済面の記事を得意としていました。
そうしているうちに、東京の大倉喜八郎という人と知り合い、明治20(1887)年「日本土木会社」へ社長秘書として入社しました。
こうして直幹は、27歳で実業界に入っていきました。
9-3 来能のいきさつ
その後、大倉喜八郎の大倉組と久次米商会が資本金を出して、東京に林産商会が創立されました。その1年後に直幹は、能代支店長として赴任しました。
明治22(1889)年4月直幹28歳の時で、いよいよ腰をすえて働く場所を得たのです。この当時能代は、まさに文明から見離された遠い所と思われていた時代でした。
しかし直幹は、大倉喜八郎から人柄や才能を認められ、厚く迎えられたことに応えたい気持ちがあり、また未開地の豊富な資源を見て開拓者精神を刺激され、能代に骨を埋める覚悟になったのでしょう。
その時直幹は、恩師松木直己の妹梅子と結婚して1年目でした。妻と幼い長女の時江を連れて、いよいよ独自の道ヘ1歩踏み出したのです。
9-4 経営の改革
能代地方におけるこの頃の木材取引きは、大ざっぱなもので、山師(山の立木を売買する人)は、勘によって木材の体積の見当をつけて売買し、人夫も木挽(こびき・木を切る人)も境界など無頓着という状態でした。
切った木は、筏で米代川を流すのですが、業者達は筏に組まれている材木を沖仲仕(おきなかし・木材を陸にあげる人)にまかせ、料理屋で酒を飲みながら取引きをしていました。
このような所へ直幹は、今中専太郎・竹村栄三郎の2人を連れて赴任し、経営の改革を行いました。今中専太郎は20歳で簿記の仕事を担当しました。
勘に頼り、大ざっぱに見積りする方法をやめて取引きを詳しく記入し、結果をはっきりさせる記帳をしていくのです。竹村栄三郎は、木曽の山々で腕を磨いた山の専門家で、山を見る目、木を切る技術に優れていて、現場を担当する直幹の片腕として働きました。
当時の能代の人で、直幹の協力者であった大坂嘉言という人は、直幹の人柄について、「先生は、毅然として犯すべからざる重みと、信念のもとに経営をすっかり新しくし、店員の指導等も明快にやったし、外部への交渉は誠意のあふれるものでした。だから着々と改革の実があがったのです。」と言っています。
直幹は、店の仕事については大小にかかわらず自ら手をかけました。
前掛けを掛け、そろばんをはじき、値段の交渉は勿論、現場に立って商品の受け渡しに立ち会ったり、商品の鑑別(かんべつ)や計算書も作るという状態でした。
こんなやり方を嫌った仲仕や木挽達は、放火したり、宴会で乱暴を働いたりする者も少なくありませんでした。しかし直幹は、能代へ来る前から、このようなことがあることは覚悟の上でしたので、ひるむことはありませんでした。
改革のなたを振った直幹は、経営をすっかり新しくすることができましたが、林産商会が解散しなければならなくなったので、一時は東京へ帰る準備をしました。
しかし、久次米商会の真心を尽くした頼みと、大倉喜八郎の励ましによって能代へ止まることにしました。これが直幹の独立する準備期となったのです。
9-5 独立と発展
その後久次米商会は経営不振におち入り、秋田方面の材木事業をやめることにしました。
このため直幹は、久次米商会の後を受け継いで、能代材木合資会社を作って独立しました。
明治30(1897)年のことです。同じ年に能代挽材(ひきざい)合資会社を創り、材木合資会社で資材の調達を行い、挽材合資会社で加工や販売を行いました。
この頃になると能代の有力者も直幹に協力する人が多くなり、かねてからの念願であった機械製材に取りかかる準備をすすめました。
まず直幹は、今の山本総合庁舎のあるあたりに広大な敷地を買い入れ、工場の建設に取りかかる一方、汽権(きかん・ボイラー)や製材機械を買い入れました。
機械1台で木挽百人の仕事に匹敵すると言われたイギリス製の最新式機械4台をはじめ、数々の設備を整え、能代の人々を驚かせました。
普段あまり感情を表に出さない直幹でしたが、この時ばかりはその喜びに頬を染めたと言われています。
ところが、最新式の機械を運転する経験者が居らず、直幹自ら、原書や辞典と首っ引きで機械操作の指導に当る等、苦労も多かったようです。
その後、直幹の事業はますます発展し、明治34(1901)年に秋田製材合資会社を創り、明治40(1907)年には、秋田製材合資会社と能代材木合資会社・能代挽材株式会社の3社を合併して、東洋一と言われる「秋田木材株式会社」が誕生したのです。
秋木は、その後も発展につぐ発展を続け、秋田支店はもとより大館・青森・東京・大阪・九州・北海道にも支店を置いて事業を行った他、満州・樺太・朝鮮にまで進出していきました。その根拠地は米代川河畔の広大な敷地にあり、林のように立並ぶ工場の煙突など、その誇らしげな姿は、名実共に東洋一の木材工場にふさわしいものでした。
直幹はまた、植林事業・電気・鉄工業にも着手し、大量にでるオガクズなどを燃料として、明治33(1900)年10月から自家発電により電灯をつけ、同41(1908)年からは能代一円に電力を供給しました。更に、労働者の労働条件の改善にも力を尽くし、労働時間の短縮・生命保険資金の管理を考え運用の規定を設けたり、職工組合の結成をすすめる等、労働者の働き易い条件作りに尽力し、大きな効果をあげました。
また、お金がなくて困っている人々を救うための社会事業である感恩講(かんのんこう)を能代でも始め、その理事長として力を尽くしました。
秋木で働く人々のためには、健全な娯楽と高尚な趣味のための集会場として偕楽社を建てたり、能力のある者を進学させるための井坂奨学会も作りました。偕楽社は新しい建物もでき、井坂奨学会は能代の有能な人材の育成に貢献しました。
このように、井坂直幹は明治22(1889)年、28歳で来能し、以来32年間人をつつむ豊かな人格と新しい時代を見通す知性と行動力をもって、束洋一の秋木を創立し、木都能代の発展に大きな功績を残しました。
直幹は大正10(1921)年7月27日、60歳で借しまれながらその一生を能代で閉じました。
尚、邸宅あとの井坂公園には昭和44(1969)年に建立された胸像や、昭和47(1972)年には井坂記念館が建てられました。
そして、井坂直幹をしのぶ数々の遺品が収められ、一般の人々にも公開されています。